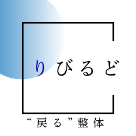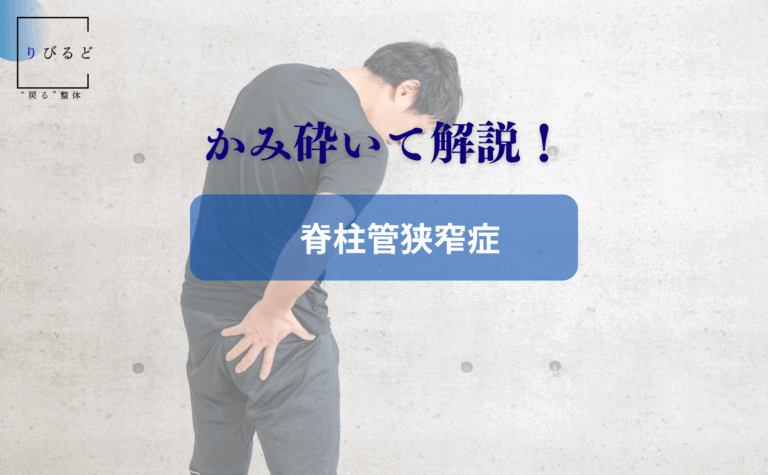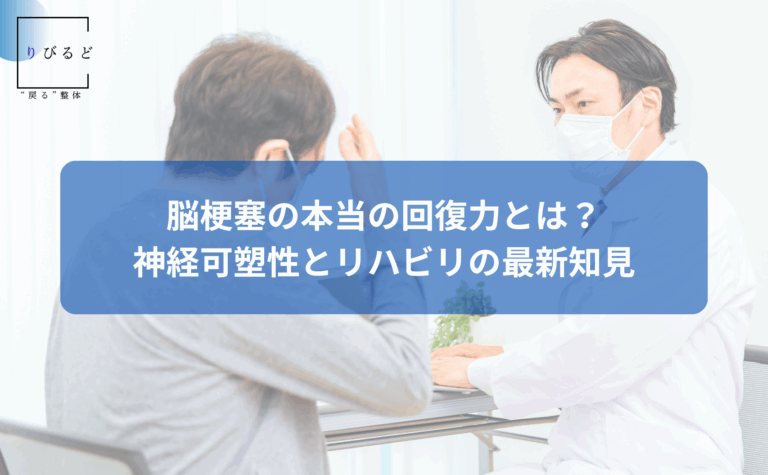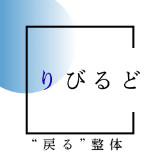膝が痛い=変形のせい?誤解されがちな変形性膝関節症の真実
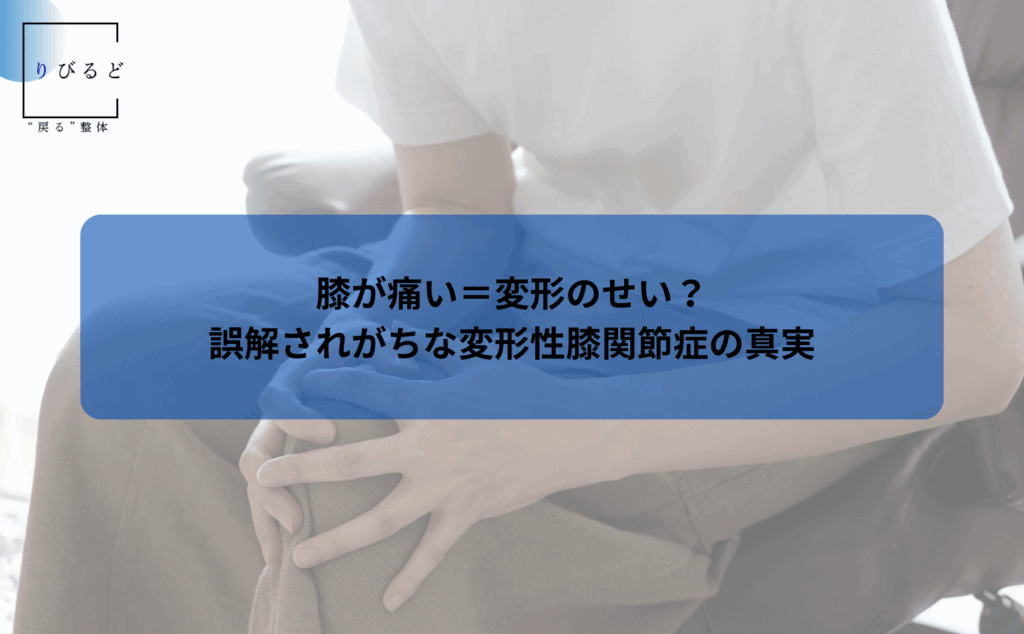
目次
第1章:変形性膝関節症とは? ― 教科書と現場のギャップ
変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう:Knee Osteoarthritis, 以下膝OA)は、中高年以降に多くみられる膝関節の慢性疾患です。国内の患者数は約1000万人以上とも言われ、潜在患者を含めれば3000万人規模に達するとの報告もあります【日本整形外科学会, 2019】。
症状としては、
- 階段を降りるときに膝がズキッとする
- 朝立ち上がるとこわばる
- 長い距離を歩いているとだんだん膝が痛くなる
こういった訴えが良く聞かれます。
教科書的には「加齢や肥満などにより関節軟骨がすり減り、骨の変形や骨棘形成を伴って膝に痛みや動きの制限を起こす」と説明されます。X線所見に基づき、Kellgren-Lawrence分類で4段階(I〜IV)に重症度を判定するのが一般的です。
しかし、実際の臨床で患者さんを診ていると「骨の変形=痛みの強さ」ではないことが多々あります。
- 画像で重度の変形があるのに痛みは軽い方
- 逆に、軽度の変形なのに強い痛みを訴える方
- 両膝とも同じ程度の変形があるのに、片膝だけが強く痛む方
👉 つまり、変形性膝関節症の痛みは「構造の変化」だけでは説明できないのです。
臨床経験から言えるのは、膝OAの症状には以下の要素が絡み合っているということです。
- 股関節や足首など他の関節の動きの制限
- 太ももやふくらはぎの筋肉の協調性低下
- 感覚のズレ(本来の荷重感覚を正しく感じられない)
- 日常生活の動作習慣(階段の昇り降り、椅子の立ち座りなど)
このように「膝の変形=痛みの原因」と単純化できないからこそ、現場では“膝を含めた全身のつながり”を見ていく必要があるのです。
※痛みについてのコラム記事はこちらから。
第2章:変形性膝関節症にまつわるよくある誤解
膝の痛みで整形外科を受診すると「軟骨がすり減っています」「年齢のせいですね」と言われることが多いでしょう。そのため、多くの方が「変形=痛みの原因」と思い込んでしまいます。しかし、臨床現場で膝の不調をみていると、実際には誤解に基づいた行動が症状を長引かせているケースも少なくありません。
誤解①「変形しているから必ず痛い」
画像で膝の変形がある=痛みの原因、と考えられがちですが、研究ではX線所見と痛みの強さは必ずしも相関しないことが報告されています【Bedson & Croft, 2008, BMJ】。
つまり、変形そのものよりも「筋力・協調性・感覚の問題」が痛みを左右している可能性が高いのです。
誤解②「歩くと膝が悪くなるから休んだ方がいい」
「膝を使わない方が摩耗を防げる」と思い込み、極端に安静にする方もいます。ところが実際には、適度な運動は膝の軟骨代謝や筋力維持に有効であり、痛みの改善にもつながることが知られています【Fransen et al., 2015, Ann Intern Med】。
歩かない生活はかえって筋力低下や体重増加を招き、症状を悪化させるリスクがあります。
誤解③「体重を減らせばすぐ痛みが取れる」
確かに肥満は膝OAの大きなリスク因子ですが、「体重を減らせば必ず痛みが消える」わけではありません。
体重減少は関節への負担を減らす効果がある一方、姿勢や動作のクセが改善されなければ痛みは残ることも多いのです。
誤解④「手術しか方法がない」
人工関節置換術は有効な選択肢ですが、すべての患者に必要なわけではありません。多くの人は、保存療法(運動療法や生活改善)で症状をコントロールできると報告されています【Zhang et al., 2010, Osteoarthritis Cartilage】。
このように、「変形=痛み」「歩かない方がいい」「手術しかない」といった思い込みは、患者さんの回復の可能性を狭めてしまいます。
大切なのは、“膝の変形”ではなく“膝を取り巻く全体のバランス”に目を向けることです。
第3章:症状のタイプと進行度の違い
変形性膝関節症(膝OA)の症状は「膝が痛い」と一言で片づけられがちですが、実際には痛み方や進み方には大きな幅があります。ここを理解しておくと、自分の状態を冷静に把握しやすくなります。
1. 初期 ― 動き始めの違和感
- 朝起きて最初の数歩が痛い
- 椅子から立ち上がる瞬間に膝がこわばる
- 長時間座ったあとに動くと「ギシギシ」する
👉 この段階では、関節軟骨の摩耗よりも関節周囲の筋肉や滑膜のこわばりが原因になっていることが多いです。
2. 中期 ― 日常生活での制限
- 階段の昇り降りで痛む
- 正座やしゃがみ込みがつらい
- 長く歩くと膝の内側がジンジンする
👉 画像上も「関節裂隙の狭小化(関節の隙間が狭くなる)」がみられ、関節の動きと荷重のバランスが崩れている段階です。
3. 進行期 ― 動き全般への影響
- 歩行距離が短くなる
- 膝の曲げ伸ばしが制限される
- 夜間痛が出て眠りを妨げる
👉 この段階では、骨棘や関節変形が進んでいることも多く、日常生活の質(QOL)に大きく影響してきます。
4. 重度 ― 動作そのものが困難に
- 常に痛みがある
- 歩行に杖や手すりが必要
- 生活全般が制限される
👉 保存療法では効果が不十分となり、人工関節置換術など外科的治療を検討するケースも増えます。
症状タイプの違い
一方で、同じ進行度でも「痛みの出方」には個人差があります。
- 荷重時痛タイプ:立つ・歩くと痛いが、安静で楽になる
- 動作制限タイプ:可動域が狭まり、曲げ伸ばしに強い制限
- 炎症タイプ:腫れや熱感が強く、安静でも痛むことがある
👉 臨床的には「進行度 × 症状タイプ」の組み合わせで、その人の困りごとが決まってきます。
まとめると、膝OAは「変形がどのくらい進んでいるか」だけでなく、痛みの質や生活での困難さによって大きく印象が変わる病気です。だからこそ、画像だけで判断せず、「その人にとって何が一番の問題か」を丁寧に見極めることが重要になります。
第4章:臨床で見えてきたポイント ― 膝だけを見てはいけない理由
変形性膝関節症の患者さんを診ていると、「膝が痛い=膝の問題」という視点だけでは不十分だと感じます。むしろ、膝以外の部位とのつながりや感覚のズレが症状を左右しているケースが多く見られます。ここでは現場で重要だと感じるポイントを紹介します。
1. 股関節の硬さが膝を追い込む
膝は“股関節と足首の中継点”です。股関節が硬いと、その動きの制限を膝が代償し、結果として過剰なストレスが集中します。
例えば「正座やしゃがみ込みで膝が痛む」ケースは、実際には股関節の屈曲制限が原因であることも少なくありません。
👉 エビデンス:股関節の可動域制限は膝OAの進行リスクと関連があることが報告されています【Chang et al., 2017, Arthritis Care Res】。
2. 足首の柔軟性と荷重感覚
足首(特に背屈の動き)が硬いと、歩行時に膝が前方へ突っ込みやすくなり、膝蓋大腿関節や内側関節への負担が増します。
さらに足裏感覚が鈍いと「どこに体重が乗っているか」が分からず、膝関節に余計な緊張が入ります。
👉 臨床的には「膝が痛いから足をかばう」のではなく、「足首が硬いから膝がかばわされている」ことも多い印象です。
3. 体幹・骨盤の安定性
骨盤や体幹の支持性が弱いと、歩行時に膝が内側や外側にブレます。
このブレが繰り返されることで、関節裂隙の一部に集中したストレスがかかり、炎症や痛みにつながります。
特に女性に多い「内股歩き」は、膝の内側OAを悪化させやすい典型例です。
4. 感覚のズレ
臨床で非常に多いのが、「膝が正しく曲がっている/伸びている感覚」が曖昧になっているケースです。
この“ズレ”があると、本来なら膝に優しい動作(例:ゆっくり立ち上がる)が、逆に痛みを増やす動作になってしまいます。
感覚の再入力を行うと、膝の負担が減り、痛みが和らぐ例を数多く見てきました。
まとめ
膝OAを診るときに忘れてはいけないのは、**「膝は単独で存在していない」**ということです。
もちろん、一般的によく言われる「膝周りの筋力低下」が痛みを引き起こす原因になっていることは多いのですが、問題の本質はそれほどタンjyんなものではありません。
股関節・足首・体幹との連動、そして感覚の在り方を含めて捉えることで、膝の痛みをより深く理解でき、改善への道が開けます。
第5章:セルフチェック ― あなたの膝はどのタイプ?
変形性膝関節症は画像だけで判断できないとお話ししました。
ここでは、日常生活で自分の膝の状態を振り返るためのセルフチェックを紹介します。該当する項目が多いほど、膝OAの可能性や進行リスクが高いと考えられます。
チェック① 朝のこわばり
- 起きて最初の数歩が痛い
- しばらく歩くと少し楽になる
👉 関節内の炎症や滑膜のこわばりが関与しているサインです。
チェック② 階段の上り下り
- 上りよりも下りで強い痛みが出る
- 膝がガクッと抜けるように感じる
👉 大腿四頭筋の協調性低下や、膝蓋大腿関節へのストレスが背景にあることが多いです。
チェック③ しゃがみ込み・正座
- 深くしゃがむと痛む
- 正座ができない/長く座れない
👉 股関節や足首の柔軟性不足が膝に過負荷をかけているケースが多いです。
チェック④ 歩行距離
- 500m以上歩くと痛みが増す
- 痛みのために休憩しないと歩き続けられない
👉 単なる変形ではなく、動作パターンや筋持久力の低下が影響している可能性があります。
チェック⑤ 膝の感覚
- 「膝が曲がっている/伸びている感じ」が分かりにくい
- 足裏の荷重感覚が左右で違う
👉 感覚のズレがあると、無意識に膝へ余計な緊張を強いてしまいます。
チェック⑥ 見た目の変化
- O脚が進んでいる気がする
- 膝の周りが腫れている
👉 骨格の変化や炎症性の腫れが進んでいる可能性があります。
チェック結果の目安
- 0〜1個:膝OAのリスクは低い。ただし油断は禁物。
- 2〜3個:初期の兆候あり。生活習慣や体の使い方を見直すタイミング。
- 4個以上:膝OAが進行している可能性大。専門家への相談がおすすめです。
このセルフチェックはあくまで目安ですが、「思い当たる項目が多い=膝を取り巻く全体のバランスに乱れがある」サイン。早めのケアで未来の動作や生活の質が大きく変わります。
第6章:セルフケアのヒント ― 膝を守る“全身づかい”の工夫
変形性膝関節症のセルフケアで大切なのは、「膝そのものを守る」こと以上に、全身で膝の負担を分散することです。膝は股関節と足首の間で働く“中継点”なので、そこだけを鍛えたり休ませたりしても限界があります。ここでは日常で取り入れやすい工夫を紹介します。
1. 股関節・足首を柔らかく使う
- 股関節ストレッチ:椅子に浅く座り、片膝を胸に軽く引き寄せる。腰を丸めすぎないよう注意。
- 足首ストレッチ:段差に足先を乗せ、かかとをゆっくり下げる。ふくらはぎの伸びを感じる程度で。
👉 股関節・足首の可動域が広がると、歩行や立ち座りで膝の負担が減ります。
2. 体重を一点に集中させない
- 椅子から立つときは「両足均等に」体重を乗せる
- 階段では「手すりを軽く使う」ことで膝の荷重を分散
- 長時間立つときは「左右に体重を移す」クセをつける
👉 膝OAの痛みは「負担の一点集中」で悪化しやすいので、小さな体重移動を習慣化すると効果的です。
3. 呼吸と姿勢を整える
呼吸が浅くなると体幹が不安定になり、膝がブレやすくなります。
- 鼻から吸い、口から長く吐く
- 吐くときに下腹がへこみ、骨盤が安定する感覚を意識
👉 「膝を守る姿勢」は実は呼吸と体幹の安定から始まります。
4. 膝まわりの優しい筋トレ
- 太もも前の軽い収縮:椅子に座って膝を伸ばし、かかとを床に軽く押す
- お尻の収縮:立った姿勢で軽くお尻に力を入れる
👉 強い負荷ではなく「日常動作の延長でできる軽い収縮」がポイント。
5. 注意点
- 強い痛みや腫れがあるときは無理に動かさない
- 痛みが和らぐ方向に「じんわり伸ばす」イメージで
- 変形や症状が進んでいる方は必ず専門家に相談する
セルフケアの目的は「膝を鍛えること」ではなく、膝が安心して動ける環境を整えることです。
毎日の小さな工夫の積み重ねが、未来の歩行や生活の質を守ることにつながります。
第7章:まとめ ― “変形を治す”より“動きを取り戻す”という考え方
変形性膝関節症は、中高年の多くが経験する身近な疾患です。
「軟骨がすり減っているから」「年齢のせいだから」と説明されることが多いため、つい「もう仕方がない」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、臨床現場で数多くの患者さんをみてきて実感するのは、痛みや動きのしづらさは“変形の程度”だけでは決まらないということです。
- 股関節や足首が柔らかく使えると膝の負担は減る
- 体幹が安定すると膝のブレは軽減する
- 感覚のズレを整えると動きの質が向上する
- 適度な運動は膝を守る方向に働く
つまり、**「膝そのものを治す」よりも「膝が本来の動きを取り戻せるように環境を整える」**ことが、痛みの改善につながります。
たとえレントゲンで変形が進んでいても、生活の工夫やセルフケアによって「まだまだ動ける膝」に変えていける可能性は十分にあります。
そしてそれは、膝だけでなく全身のつながりを見直すことから始まります。
“治す”ではなく“戻る”。
膝が本来持っている「動ける力」を引き出すこと。これが、変形性膝関節症と長く付き合っていくための本質だと私は考えています。