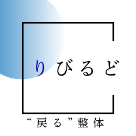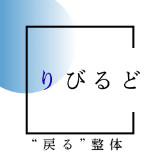かみ砕いて解説!「肩関節周囲炎」

目次
第1章:肩関節周囲炎とは? ― 教科書と現場のズレ
一般的に「四十肩・五十肩」と呼ばれる肩関節周囲炎は、40〜60代を中心に発症する肩の痛みと可動域制限を特徴とする疾患です。医学的には「関節包や靭帯、腱板など肩周囲の組織に炎症や癒着が起こることで、肩が動かなくなる状態」と説明されます。実際、整形外科の教科書にも「原因不明の肩関節周囲の炎症」「進行期には関節包の拘縮を伴う」といった言葉が並びます。
ところが、臨床の現場で患者さんを診ていると、必ずしも「肩の組織が固まっているから動かない」というシンプルな話ではありません。
実際には、
- 炎症期の鋭い夜間痛
- 拘縮期の動かそうとすると突っ張る感覚
- 回復期に残る微妙な可動域制限や違和感
と、ステージごとに症状の出方や困りごとは異なります。
さらに「肩だけの問題」では済まないケースも多いのが実際です。例えば胸椎や肩甲骨の可動性が低下していると、肩の動きそのものが制限され、必要以上に関節包へ負担がかかります。また、姿勢や日常動作のクセによって「痛みのトリガー」が作られているケースもあります。
つまり、肩関節周囲炎は“肩の病気”というより“肩を中心とした動きのシステムの不調和”と捉える方が臨床的にはしっくりくるのです。
第2章:肩関節周囲炎にまつわるよくある誤解
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)に悩む方から、臨床現場ではしばしば次のような言葉を耳にします。
- 「肩の骨や軟骨がすり減ったから、もう治らない」
- 「関節が完全に固まってしまったから、一生このまま」
- 「痛みを我慢してでも、無理に動かした方が早く良くなる」
一見もっともらしく思えるこれらの言葉ですが、実際には誤解であることが少なくありません。
誤解①「骨や軟骨の変形が原因」
レントゲンを撮ると、多くの場合「異常なし」と言われます。肩関節周囲炎は主に関節包や靭帯、腱板などの軟部組織の問題であり、骨や軟骨の変形そのものが原因ではありません。
→ ここで大事なのは「画像上の所見と症状は必ずしも一致しない」ということです。
誤解②「固まったら一生治らない」
確かに拘縮期は肩の可動域が大きく制限されます。しかし臨床経験からも、時間の経過と適切なアプローチにより可動域は回復していく例が多いです。むしろ“固まった”状態をどう乗り越えるかがポイントになります。
誤解③「痛くても動かした方がいい」
「動かさないと固まる」と言われ、痛みをこらえて強引にストレッチする方もいます。ですが炎症が強い時期に無理に動かすと、かえって炎症を悪化させることが少なくありません。
→ 大切なのは「炎症期は休ませる」「拘縮期以降は少しずつ感覚を取り戻しながら動かす」といった段階的な対応です。
このように、肩関節周囲炎は「知っているつもり」で誤った理解をしてしまいがちです。誤解を持ったまま無理をすれば、症状を長引かせる原因にもなります。逆に言えば、正しい知識と対応を知ることで「本来の回復力」を引き出すことができるのです。
第3章:タイプ別にみる肩関節周囲炎 ― 症状と実感のズレ
肩関節周囲炎は、医学的にも 炎症期 → 拘縮期 → 回復期 といった経過をたどると説明されます。ただし、臨床現場で実際に患者さんから話を聞くと「教科書通りにきれいに移行するケース」はむしろ少数派です。症状の強さや持続期間、困りごとの内容は人によって大きく異なります。
1. 炎症期(急性期)
- 特徴:夜間痛が強く、じっとしていてもズキズキ痛む。寝返りを打つだけで目が覚めることも。
- 患者さんの実感:「寝不足で日中も辛い」「肩を動かさなくても痛いから不安になる」
- 臨床的ポイント:無理に動かすのは逆効果。炎症が落ち着くまで患部を安静にし、冷却や生活動作の工夫が必要。
2. 拘縮期(慢性期)
- 特徴:炎症のピークは過ぎるが、肩を上げたり後ろに回したりすると突っ張る。動きの制限が顕著になる。
- 患者さんの実感:「痛みは落ち着いてきたけど、動かない」「髪を結ぶ・服を着るのがつらい」
- 臨床的ポイント:ここでのアプローチは感覚を取り戻しながら可動域を広げること。強引なストレッチはNGだが、動作の中で少しずつ肩と胸郭・肩甲骨を連動させていくことが重要。
3. 回復期
- 特徴:日常動作はかなり改善するが、細かい動作や最後の可動域で違和感が残ることがある。
- 患者さんの実感:「日常生活は困らないけど、万歳した時に突っ張る」「完全に元通りではない気がする」
- 臨床的ポイント:肩だけでなく、胸椎や肋骨、股関節など全身の連動性を再構築することが、違和感の解消につながる。
このように「肩関節周囲炎」と一言でまとめられても、実際にはステージごとに“困りごと”が違います。さらに、患者さんの多くは「痛みが強い時期に無理をして悪化」「拘縮期に動かさなすぎて固まる」といった“実感と対応のズレ”を経験しています。
だからこそ、 症状の段階を見極め、その人に合ったアプローチを選ぶことが回復への近道 になるのです。
第4章:臨床で見えてきたポイント ― 肩だけにとらわれない視点
肩関節周囲炎を診ていると、単に「肩の関節包が固まっている」という説明では片付けられないことが多くあります。実際の患者さんをみる中で特に重要だと感じるのは、感覚のズレ・胸椎や肩甲骨の硬さ・日常動作のクセ の3つです。
1. 感覚のズレ
「痛みがあるから動かせない」というよりも、「本来の位置感覚を失っている」ケースが多々あります。
たとえば「肩を上げているつもりでも、実際には首や背中の筋肉にばかり力が入っている」ようなパターンです。
このように脳が正しい動きを認識できなくなると、肩の動きは制限されてしまうのです。
2. 胸椎や肩甲骨の硬さ
肩関節は単独で動くものではなく、胸椎の伸展や肩甲骨の回旋がうまく連動してはじめてスムーズな動きが生まれます。
実際、胸椎が硬い人ほど「肩を上げようとすると詰まる感じがする」と訴えることが多いです。
→ この場合、肩そのものを無理に動かすよりも胸椎や肩甲骨の自由度を高める方が早く改善につながることもあります。
3. 日常動作のクセ
臨床でよく見かけるのが「内旋・巻き肩」の姿勢や「長時間のデスクワーク」。
このような習慣は、肩の前方構造を常に緊張させ、肩関節に余計な負担をかけます。
さらに「痛いから使わない」→「固まる」→「ますます動かない」という悪循環に陥る方も少なくありません。
つまり肩関節周囲炎の本質は、“肩の病変”というより“全身の動きと感覚のアンバランス” にあります。
臨床では「肩を診る」のではなく「肩を含めた全体の動きを診る」ことが改善への大きなカギになるのです。
第5章:セルフチェック ― あなたの肩は大丈夫?
肩関節周囲炎は、人によって症状の出方や進行の仕方が大きく異なります。そこでまずは、次のセルフチェックでご自身の状態を確認してみましょう。
チェック① 寝返りの痛み
仰向けから横向きに寝返りを打ったときに「肩のズキッとした痛み」で目が覚めることはありませんか?
→ これは炎症期に多く見られるサインです。夜間痛は生活の質を大きく下げるため、早めの対応が必要です。
チェック② 背中に手を回せるか
ズボンの後ろポケットや、腰の後ろに手を回してみましょう。
「途中で引っかかる」「痛みでこれ以上いけない」という場合は、肩の内旋・内転方向の制限が疑われます。
チェック③ 万歳がスムーズにできるか
両腕を耳に近づけるように真上にあげてみてください。
- 腕が途中で止まってしまう
- 代わりに腰を反らさないと上がらない
→ このような場合、肩関節だけでなく胸椎や肩甲骨の動きが制限されている可能性があります。
チェック④ 日常動作での不便
- 髪を結ぶ動作がつらい
- 洗濯物を干すときに肩が上がらない
- ジャケットを着るときに腕が回らない
→ これらは拘縮期に多い訴えで、「生活の中での困りごと」として症状を実感しやすいポイントです。
これらのチェックでいくつか当てはまる方は、すでに「肩関節周囲炎の流れに入っている」可能性があります。ただし、セルフチェックで全てが分かるわけではありません。大切なのは「痛みや動かしづらさを放置しない」こと。早めに気づくことが、回復をスムーズにする第一歩です。
第6章:セルフケアのヒント ― 無理に伸ばさず“感覚”を取り戻す
肩関節周囲炎のセルフケアで一番大事なのは、「痛みに逆らわない」ことです。
よく「固まるから無理にでも動かさなきゃ」と考える方がいますが、それは逆効果になることもあります。特に炎症期は組織が敏感になっているため、強い刺激を与えると炎症が長引きかねません。
ここでは、比較的安全に取り入れやすいセルフケアのポイントを紹介します。
1. 炎症期は“休ませる工夫”
- 横向きで寝るときは、抱き枕やクッションを胸の前に置き、腕を支えてあげる
- 冷却(アイシング)で痛みをコントロールし、夜間痛を軽減する
→ ポイントは「動かさずとも痛みを減らす」工夫です。
2. 拘縮期は“小さな動き”から
- テーブルの上に腕を置き、体を前に少しずつ倒して肩を前に出す「テーブルスライド」
- 壁に指先を当てて、痛みのない範囲で指を歩かせる「ウォールウォーキング」
→ これらは肩そのものを無理に伸ばすのではなく、体全体の動きを利用して肩に“動ける感覚”を思い出させる方法です。
3. 回復期は“連動性を意識”
- 肩だけを動かすのではなく、胸を広げながら腕を上げる
- 呼吸を合わせて、息を吐きながら動かす
→ 「肩を動かす」というより「胸と肩甲骨と一緒に動く」感覚を養うことが、違和感の解消につながります。
注意点
- 痛みが鋭く走る動きは避ける
- 「少し気持ちいい」「じんわり伸びる」くらいを目安にする
- 改善しない場合や夜間痛が強い場合は、自己流で続けず専門家に相談する
セルフケアは「関節をこじ開ける作業」ではなく、**「失われた感覚を取り戻す作業」**と捉えると安全で効果的です。
第7章:まとめ ― “治す”より“戻る”という視点を
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)は、教科書的には「原因不明の肩の炎症」と一括りにされます。しかし実際には、
- 炎症による強い夜間痛
- 拘縮による動かしづらさ
- 回復期に残る違和感や可動域の制限
といった 段階ごとの困りごと があり、しかもその経過は人によって大きく異なります。
また、症状を長引かせる最大の要因は「誤解」と「対応のズレ」です。
「骨や軟骨が原因だと思い込む」「痛みを我慢して動かす」「放置すれば自然に治る」といった考え方は、回復を妨げてしまうこともあります。
臨床経験から強く感じるのは、肩関節周囲炎を本当に改善へ導くためには、肩そのものだけを見るのでは不十分だということです。
胸椎や肩甲骨の動き、日常の姿勢や動作のクセ、そして「正しい感覚を取り戻すこと」。これらを整えることで、肩は“本来の状態”へと戻っていきます。
だからこそ大切なのは、「治す」ではなく「戻る」 という視点です。
無理に力で押し広げるのではなく、身体がもともと持っている回復力を引き出す。そんな関わり方が、肩関節周囲炎と向き合ううえで一番の近道だと考えています。
ご自身の方について、心配なことがあればいつでもお気軽にご相談ください。